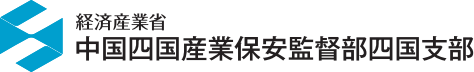電気主任技術者の選任
条件の内容につては、次のリンク先をご参照ください。
主任技術者の選任(自社、関係会社、ビル管理会社等の社員から選任、兼任する場合)
自家用電気工作物の設置者は、原則として事業場ごとに主任技術者免状の交付を受けている者の中から主任技術者を選任しなければなりません。
主任技術者には、電気主任技術者、ダム水路主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者の区分があり、設備の状況に応じて必要な主任技術者を選任しなければなりません。このうち電気主任技術者はすべての自家用電気工作物の事業場で選任が必要であり、選任には次の方法があります。
- 事業場の有資格者から選任する(選解任届)
- 保安監督を行う能力があると認められる者を許可を受けて選任する(選任許可)
- 他の事業場で選任されている者を承認を受けて兼任させる(兼任承認)
- 管理技術者又は電気保安法人に保安管理業務を外部委託する(外部委託承認)
※ダム水路主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の選任については、担当者にお問い合わせください。
有資格者から選任する場合(電気事業法第43条第1項)
社内の有資格者から選任する場合
設置者(みなし設置者を含む)の社員に電気主任技術者免状の交付を受けている者がいる場合には、その者を電気主任技術者として選任することができます。なお、建設現場等で使用する移動用電気工作物に係る主任技術者の選任は移動用電気工作物を管理する本店、支店、営業所ごとに選任することができます。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類 |
|
| 届出時期 | 選任後、遅滞なく(原則として1か月以内) |
| 条件 |
|
関連会社の有資格者を選任する場合
設置者の関連会社に電気主任技術者免状の交付を受けている社員がいる場合には、その者を電気主任技術者として選任することができます。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類 |
|
| 届出時期 | 選任後、遅滞なく(原則として1か月以内) |
| 条件 |
|
派遣労働者又は設備管理会社(ビルメンテナンス会社)等の社員から選任する場合
事業場に常駐する派遣労働者又は自家用電気工作物を含む事業場の設備管理を委託している設備管理業者の社員で、電気主任技術者免状の交付を受けている者がいる場合は、その者を主任技術者に選任することができます。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類 |
|
| 届出時期 | 選任後、遅滞なく(原則として1か月以内) |
| 条件 |
|
有資格者以外の者を選任する場合(電気事業法法第43条第2項)
設置者(みなし設置者を含む)の社員のうち、電気主任技術者免状の交付を受けていない者であっても、小規模な事業場であれば、第一種電気工事士免状取得者等、電気工作物について保安監督を行う知識及び技能があると認められる場合は、産業保安監督部長の許可を受けて主任技術者として選任することができます。なお、建設現場等で使用する移動用電気工作物に係る主任技術者の選任は、移動用電気工作物を管理する本店、支店、営業所ごとに選任することができます。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類 |
|
| 申請時期 | 選任しようとする前 |
| 条件 |
|
既に選任している者を兼任させる場合(電気事業法施行規則第52条第4項)
社内の主任技術者を兼任させる場合
既に選任している主任技術者であっても、最大電力2,000キロワット未満かつ6事業場まで(選任事業場含む)であれば、同一設置者(みなし設置者を含む)が設置する他の事業場の主任技術者に産業保安監督部長の承認を受けて兼任させることができます。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類 |
|
| 申請時期 | 兼任しようとする前 |
| 条件 |
|
関連会社の主任技術者を兼任させる場合
関連会社が既に選任している主任技術者であっても、最大電力2,000キロワット未満かつ6事業場(選任事業場含む)までであれば、関連会社が設置する他の事業場の主任技術者に産業保安監督部長の承認を受けて兼任させることができます。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類 |
|
| 申請時期 | 兼任させようとする前 |
| 条件 |
|
派遣労働者又は設備管理会社(ビルメンテナンス会社)等から選任されている主任技術者を兼任させる場合
設置者が既に選任している派遣労働者又は既に選任している設備管理会社の社員であっても、最大電力2,000キロワット未満かつ6事業場(選任事業場含む)までであれば、派遣労働者又は設備管理会社の社員を同一設置者が設置する他の事業場の主任技術者に産業保安監督部長の承認を受けて兼任させることができます。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類 |
|
| 申請時期 | 兼任させようとする前 |
| 条件 |
|
同一敷地内に設置されている別会社の主任技術者を兼任させる場合
同一敷地内に設置者の異なる自家用事業場が複数設置されている場合(工場の屋上に設置された屋根貸し太陽電池発電所等)であっても、最大電力2,000キロワット未満かつ6事業場(選任事業場含む)までであれば、産業保安監督部長の承認を受けて兼任させることができます。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類 |
|
| 申請時期 | 兼任させようとする前 |
| 条件 |
|
外部委託承認申請(保安法人、管理技術者に外部委託する場合)
出力2,000キロワット未満(燃料電池は1,000キロワット未満)の発電所、7,000ボルト以下で受電する需要設備、600ボルト以下の配電線路を管理する事業場においては、電気主任技術者を選任する代わりに、産業保安監督部長の承認を受けて、保安管理業務を管理技術者または電気保安法人に委託することができます(保安管理業務の外部委託)。保安管理業務の外部委託を行う場合は、外部委託承認申請を行ってください。
なお、保安管理業務の外部委託を行うためには委託先が電気事業法施行規則第52条の2の要件を満たす必要があり、この確認には主任技術者制度の解釈及び運用(内規)に定められた審査基準が用いられます。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類 |
共通書類
委託先が個人で初回受託の場合
委託先が保安法人で初回受託の場合
|
| 申請時期 | 委託による管理を開始する前 |
| 条件 |
委託先が電気事業法施行規則第52条の2の要件を満たすこと 関連告示及び内規
参考: |
保安規程
保安規程届出
電気事業法第42条第1項の規定により、自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保のため、保安規程を作成し産業保安監督部長に届け出て下さい。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類 |
|
| 届出時期 | 電気工作物の使用の開始前まで(使用前自主検査等を伴うものにあっては工事の開始前まで) |
| 保安規程に記載すべき事項 |
|
保安規程変更届出
自家用電気工作物の設置に伴い定めた保安規程の内容を変更した場合は、電気事業法第42条第2項の規定により、変更した事項を遅滞なく届け出て下さい。なお、保安規程そのもの自体とみなされない細則中の事項や、字句の修正等、実質的に保安業務に影響しない軽微な事項は保安規程中に記載されてあっても変更の届出は必要ありません。
次のような場合は通常、保安規程変更届出が必要になります。
- 保安に関する組織、業務分掌、指揮命令系統等の保安規制を変更した場合
- 発電所(火力、太陽電池、燃料電池)又は非常用発電機を設置した場合
- 電力会社との責任、財産分界点を変更した場合
- 自家用構内を拡張又は縮小した場合
- 外部委託法人等に委託していたのを、自社から電気主任技術者を出すように変更した場合、またはその逆の場合
- 電気主任技術者を自社で選任していたのを、ビル管理会社から選任した場合、その逆の場合
- 法定自主検査を初めて実施する場合
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類 |
|
| 届出時期 | 変更後、遅滞なく(原則として1か月以内) |
変更に係わる諸報告
廃止報告
自家用電気工作物を設置する事業場を廃止した場合には、電気関係報告規則第5条第2号に基づく報告(自家用電気工作物廃止廃止報告)が必要です。
設備の一部の廃止の場合は廃止報告の必要はありませんが、廃止する設備がばい煙発生施設等の特定施設の場合は、電気関係報告規則第4条の表第17号の規定にる届出(特定施設等使用廃止届出)が必要となります。なお、廃止する設備が発電設備の一部の廃止で発電所の出力変更を伴う場合は、電気関係報告規則第5条第1号に基づく報告(自家用電気工作物出力(又は電圧)変更報告)となります。
自家用電気工作物廃止報告
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 報告対象 |
|
| 報告の時期 | 廃止後遅滞なく(原則として1か月以内) |
特定施設等使用廃止届出
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 届出対象 |
|
| 報告の時期 | 廃止後遅滞なく(原則として1か月以内) |
使用開始届出
受電電圧1万ボルト以上の需要設備やばい煙(騒音・振動)発生施設等を他から譲り受けて、または借り受けて使用する場合は自家用電気工作物使用開始届出が必要です。
必要な添付書類など使用開始届の手続きの詳細については、対象となる設備の担当者にお問い合わせ下さい。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 届出対象 |
|
ばい煙発生施設設置届出
ばい煙発生施設を他から譲り受けて、または借り受けて使用する場合は、ばい煙発生施設設置届出が必要となります。
ばい煙発生施設には、1時間あたりの燃料消費量(重油換算)が、ディーゼル機関及びガスタービンについては50リットル以上、ガス機関及びガソリン機関については35リットル以上のものが該当します。
※重油換算量:液体燃料は10リットル、ガス燃料は16立方メートル、固体燃料は16キログラムが重油10リットルに相当
必要な添付書類などの手続きの詳細については、対象となる設備の担当者にお問い合わせ下さい。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 届出対象 |
|
氏名等変更届出
ばい煙(騒音・振動)発生施設など公害特定施設に該当する電気工作物を設置している事業場において、設置者の名称、設置者の本社住所、事業場の名称、事業場所の在地、法人にあっては代表者の氏名に変更があった場合は、電気関係報告規則に基づく氏名等変更届出が必要です。
それ以外の場合、法令に基づく届出の必要はありませんが、管内の事業場の管理を確実にするため、任意様式で変更内容の連絡をお願いします(名称等変更報告)。
電気関係報告規則に基づく氏名等変更届出
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 届出対象 |
|
| 報告の時期 | 廃止後遅滞なく(原則として1か月以内) |
名称等変更報告
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 報告の対象 |
|
| 届出の時期 | 変更後遅滞なく(原則として1か月以内) |
※名称等変更報告はFAX等での提出で構いません
地位承継届出
自家用電気工作物を設置する者について、相続によりその地位承継した場合、または法人の合併等によりその地位を承継した場合には、電気事業法第55条の2第2項の規定に基づく事業用電気工作物地位承継届出が必要です。
手続きの詳細については、リンク先を参照するとともに、対象となる設備の担当者にお問い合わせ下さい。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 届出の対象 |
|
出力等変更報告
発電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合は、自家用電気工作物出力(又は電圧)変更報告が必要です。
ただし、電気事業法第47条の工事計画の認可または同法第48条の工事計画の届出の手続きが行われた場合は、本手続きは不要です。
なお、発電設備の一部の廃止で発電所としての出力が変更になる場合は、廃止報告ではなく本手続きにより報告を行うことになります。
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 届出の対象 |
|
工事計画、使用前安全管理審査と使用前自己確認
工事計画届出
自家用電気工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、電気事業法第48条の規定に基づき工事計画届出を行う必要があります。経済産業令で定める工事は、電気事業法施行規則の別表第2の下欄及び別表第4の上欄(ばい煙発生施設など特定施設に係る工事計画届出)で定められています。
工事計画届出は工事の開始30日前までに行う必要があります。※
工事計画届出にあたっては、事前に対象設備の担当者に連絡をしてください。
※工事計画届出日と工事の開始日
工事計画届出日は、届出書に記載された日でなく、電力安全課にて届出を受理した日となります。また、工事の開始日は、通常は対象となる電気工作物の基礎工事を開始する日となります。例えば、5月31日に工事計画の届出(電力安全課で届出の受理)が行われた場合、7月1日から工事開始可能となります。
工事計画届出
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類等 |
|
| 対象工事 | 電気事業法施行規則別表第2下欄の工事
需要設備の場合の工事例
|
| 届出の時期 | 工事開始の30日前まで |
ばい煙発生施設など特定施設に係る工事計画届出
| 様式等 | 内容 |
|---|---|
| 様式 |
|
| 添付書類等 |
|
| 対象工事 | 電気事業法施行規則別表第4上欄の工事
工事例
|
| 届出の時期 | 工事開始の30日前まで |
法定自主検査と安全管理審査
特定の工事や電気工作物の使用については、設置する事業者が検査(法定自主検査)を行い、その検査の体制について安全管理審査を受けることが義務付けられています。なお、電気事業法施行規則の改正に伴い、令和5年(2023年)3月20日から登録安全管理審査機関が実施することとなりました。
- 電気工作物の設置や変更の工事において、工事計画届出に該当する工事であって経済産業省令で定める電気工作物を設置する場合は、その使用の開始前に事業者による検査(使用前自主検査)を行うとともに、その検査の体制について使用前安全管理審査を受けなければなりません。
- 特定ボイラー等として定められる機械や器具の溶接は、事業者による検査を行い(溶接事業者検査)、その検査の体制について溶接安全管理審査を受けなければなりません。
- 経済産業省令で定める特定電気工作物については、定期的に事業者による検査を行い(定期事業者検査)、その検査の体制について定期安全管理審査を受けなければなりません。
法定自主検査の実施
法定自主検査は、保安規程に実施に係る事項を定め適切に実施する必用があります。
検査の実施に関し、検査対象や実施の時期、検査の内容、検査の記録方法、安全管理審査を受ける時期等が、電気事業法施行規則に検査の種類毎に定められてます。また、経済産業省の内規として施行規則の解釈や検査のガイドを定めています。
使用前自主検査
- (電気事業法施行規則第73条の2の2)検査の対象
- (電気事業法施行規則第73条の3)検査の時期
- (電気事業法施行規則第73条の4)検査の方法
- (電気事業法施行規則第73条の5)検査の記録方法
- (電気事業法施行規則第73条の6)安全管理審査を受ける時期
- (電気事業法施行規則第73条の6の2から第73条の6の9まで)安全管理審査に係る事項
- 電気事業法施行規則第73条の4に定める使用前自主検査の方法の解釈(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:835KB)

- 電気事業法施行規則第73条の4に定める使用前自主検査の方法の解釈(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:15,713KB)
 (平成24年12月31日以前)
(平成24年12月31日以前)
溶接事業者検査
- (電気事業法施行規則第79条から第81条まで)検査の対象象
- (電気事業法施行規則第82条)検査の方法
- (電気事業法施行規則第83条)検査の記録方法
- (電気事業法施行規則第84条)検査対象の適用除外
- (電気事業法施行規則第84条の2)安全管理審査を受ける時期
- (電気事業法施行規則第84条の3から第86条まで)安全管理審査に係る事項
- 電気事業法施行規則に基づく溶接事業者検査(火力設備)の解釈(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:****KB)

- 電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:1,763KB)

定期事業者検査
- (電気事業法施行規則第94条)検査の対象
- (電気事業法施行規則第94条の2)検査の時期
- (電気事業法施行規則第94条の3)検査の方法
- (電気事業法施行規則第94条の4)検査の記録方法
- (電気事業法施行規則第94条の5)安全管理審査を受ける時期
- (電気事業法施行規則第94条の5の2から第94条の7まで)安全管理審査に係る事項
- 電気事業法施行規則第94条の3第1項第1号及び第3号に定める定期事業者検査の方法の解釈(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:357KB)

- 電気事業法施行規則第94条の3各号の解釈例(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:163KB)
 平成23年4月3日以前
平成23年4月3日以前
※定期事業者検査の実施時期については、時期変更を行うことが可能な場合があります。
安全管理審査
使用前・定期安全管理審査実施要領
- 使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:610KB)

- 使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:336KB)
 平成24年9月18日以前
平成24年9月18日以前 - 安全管理審査実施要領(内規)(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:71KB)
 平成23年3月31日以前
平成23年3月31日以前
溶接安全管理審査実施要領
FAQ等
- 安全管理検査制度に係るQ&A集(経済産業省ウェブサイト)

- 使用前・定期安全管理検査の運用改善に係るQ&A集(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:946KB)

- よくある質問(溶接安全管理審査の運用改善)(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:744KB)
 平成24年9月18日以前
平成24年9月18日以前
申請先
| 審査区分 | 出力15万キロワット未満の火力発電設備に属する電気工作物 | それ以外 |
|---|---|---|
| 使用前安全管理審査 | 登録安全管理審査機関 | 経済産業省 |
| 溶接安全管理審査 | 登録安全管理審査機関 | 登録安全管理審査機関 |
| 定期安全管理審査 | 登録安全管理審査機関 | 経済産業省 |
安全管理審査申請様式
- (電気事業法施行規則様式第52の2)使用前安全管理審査申請書
- (電気事業法施行規則様式第62)定期安全管理審査申請書
安全管理審査手数料
安全管理審査の手数料は、電気事業法関係手数料規則に安全管理審査の種類に応じて定められています。
対象設備により納入方法が異なりますので、安全管理審査申請前に設備の担当者にお問い合わせください。
- (電気事業法関係手数料規則第2条の2)使用前安全管理審査に係る手数料
- (電気事業法関係手数料規則第6条)定期安全管理審査に係る手数料
使用前自己確認
平成28年4月から、一部の電気設備について従来必要であった工事計画を不要とし、設置者による設備使用前の確認の結果を国に届け出る使用前自己確認制度が新設されました。
また、近年、中小規模の太陽電池発電設備について、突風や台風等によるパネルの飛散により近隣の家屋等の第三者への被害が発生している状況を踏まえ、平成28年11月30日から、出力500キロワット以上2,000キロワット未満の太陽電池発電設備についても、使用前自己確認制度が導入されました。
更に、再エネ発電設備の適切な保安を確保するため、太陽電池発電設備(10キロワット以上50キロワット未満)、風力発電設備(20キロワット未満)を小規模事業用電気工作物と新たに区分し、これら小規模事業用電気工作物は、令和5年3月20日に、技術基準適合維持義務、基礎情報の届出、及び使用前自己確認が義務化されます。加えて、使用前自己確認の対象外だった太陽電池発電設備(50キロワット以上500キロワット未満)についても、使用前自己確認が義務化されます。
使用前自己確認
使用前自己確認制度は、経済産業省令で定める電気工作物の工事について、使用の開始までに結果を国に届け出る必要があります。
自己確認の実施に関し、対象や実施の時期、内容等が、電気事業法及び施行規則に定められてます。また、経済産業省の内規として自己確認の方法の解釈等について定めています。
- (電気事業法施行規則第74条、第77条)対象の電気工作物
- (電気事業法施行規則第76条)自己確認の方法
- (電気事業法第51条の2第3項)届出の時期
- (電気事業法施行規則第78条第1項)届出の内容
- (電気事業法施行規則第78条第2項)自己確認の結果の保存
定期事業者検査時期変更
電気工作物の使用状況によっては、産業保安監督部長の承認を得て定期事業者検査の時期を延長することができます。
条件や延長の時期については、次の審査基準を参照してください。
- (電気事業法施行規則様式第61の2)時期変更承認申請書
管理技術者
管理技術者等になるための手続き
管理技術者、保安業務従事者とは
電気事業法では、事業者が設置する事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)の工事、維持、運用に関する保安の監督をさせるため、原則として電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、電気主任技術者を選任することが定められています。
管理技術者(保安業務従事者)とは、電気事業法施行規則第52条の2に定められた、自家用電気工作物の電気保安に関する業務を行う者のことであり、個人事業者の場合は管理技術者、保安法人に所属している場合は保安業務従事者と呼びます。
自家用電気工作物を有する事業者等は、管理技術者又は保安法人との契約によって電気主任技術者の選任が不要となります。
管理技術者、保安業務従事者の要件
規則第52条の2に定められている要件
- 電気主任技術者免状の交付を受けていること
- 電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間が、通算して次に掲げる期間以上であること。
- 第一種電気主任技術者免状の交付を受けている人 3年
- 第二種電気主任技術者免状の交付を受けている人 4年
- 第三種電気主任技術者免状の交付を受けている人 5年
- 告示に記載がある機械器具を有していること(絶縁抵抗計、電流計、電圧計 等)
※保安法人が所有している場合は、個人所有する必要なし - 保安管理業務の的確な遂行に支障がないこと(他に職業を有していないことの説明書)
- 保安管理業務外部委託承認取消の責めに任ずべき者であってその取消の日から2年を経過しない者でないこと
- 保安法人であれば、雇用証明書
- 平成十五年経済産業省告示第二百四十九号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示)(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:163KB)

- 主任技術者制度に関するQ&A(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:846KB)

自家用電気工作物に関する実務について
電気主任技術者が外部委託制度において業務を受託するには、電気主任技術者免状の取得に加え、一定期間以上の実務経験を有していることについて経済産業省の確認を受ける必要がありますが、当該実務経験の期間の算定方法と確認の際に提出が必要な書類等については、以下のウエブサイトを御参照ください。
証明者から代表印をいただく前に、実務経験が自家用電気工作物の工事、維持又は運用に該当する経験かどうか確認する必要がありますので、事前に当課までE-MAILにてご連絡ください。
- 宛先
- bzl-qsikps@meti.go.jp
- 件名
- 管理技術者(保安業務従事者)の実務経験確認依頼
- 担当
- 中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課
- 添付書類
- 実務経歴証明書(代表者印がないもの)
電気保安法人一覧
| 電気保安法人名 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|
| 一般財団法人四国電気保安協会 | 〒761-0301 高松市林町331番地2 | 087-805-1670 |
| 協同組合愛媛電気保安協会 | 〒799-2201 今治市大西町九王甲272-1 | 0898-36-2016 |
| 有限会社米倉電気管理事務所 | 〒770-8070 徳島市八万町馬場山43-2 | 088-668-6650 |
| 四国ビル総合管理株式会社 | 〒761-8042 高松市御厩町1551-1 | 087-870-4255 |
| 徳島県木材団地協同組合連合会 | 〒770-8001 徳島市津田海岸町8-20 | 088-662-3711 |
| 株式会社中央メンテ | 〒799-0405 四国中央市三島中央3丁目10番2号 | 0896-24-1870 |
| 有限会社長尾電気メンテナンス | 〒779-3603 美馬市脇町大字猪尻字土井80 | 0883-53-0219 |
| 株式会社中央電気保安協会 | 〒791-8071 松山市松ノ木町1-5-40 | 089-968-3832 |
| 有限会社新電気技術 | 〒781-0303 高知市春野町弘岡下3904-2 | 088-894-4757 |
| 日本テクノ株式会社 | 〒760-0019 高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー12階 | 087-811-6185 |
| 一般社団法人徳島地域エネルギー | 〒771-4102 名東郡佐那河内村上字仁井田100-2 | 050-2024-5033 |
| 株式会社四国電気保安システム | 〒791-8043 松山市東垣生町897番地1 | 089-968-6672 |
| 太平ビルサービス株式会社 | 〒760-0056 高松市中新町2-9 富士ビル8階 | 087-834-7243 |
| 株式会社芝原電気メンテ | 〒771-0123 徳島市川内町鈴江北126 | 088-665-4107 |
| 旭テクノプラント株式会社 | 〒710-0038 岡山県倉敷市新田2403-1 | 086-430-0123 |
| 日本エネルギー総合システム株式会社 | 〒761-0301 高松市林町1964-1 | 087-813-5908 |
| オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント株式会社 | 〒135-0042 東京都江東区木場1-4-12 | 03-6666-7501 |
※掲載されている電気保安法人は、当部が当該法人の活動に対し認可、許可その他の行政行為(法令上の権利設定)を行っているものではありません。
※掲載されている電気保安法人の要件確認は、過去の外部委託承認申請時に行ったものであるため、現時点においても要件を満たしていることを保証するものではありません。
※事業場までの到達時間等の条件により、委託できない場合があります。
ケース別手続き概要
| ケース | 必要な手続き |
|---|---|
| 事業場を新設する場合 (例)工場を建設する、店をオープンする、ビルを建てる、テナントビルに入居するなど |
電電圧1万ボルト未満の需要設備、出力2,000キロワット未満の太陽電池発電設備、風力発電所
|
| 事業場を譲渡、譲受した場合 (例)工場を購入した、店を買った、ビルを買ったなど |
受電電圧1万ボルト未満の需要設備、出力2,000キロワット未満の太陽電池発電設備、風力発電所
|
| 可搬型の発電設備を設置する場合 (例)建設現場やイベント会場等で、リース会社から可搬型(出力10KW以上の内燃力を原動力とするもの)の発電設備を借り受けて据え付けるような場合 |
電気主任技術者免状の交付を受けている者を選任する場合
|
| 主任技術者を選任(兼任・許可)から外部委託に変更した場合 |
|
| 設置者法人の社名、所在地、代表者、事業場名、事業場所在地を変更した場合 |
|
| 責任分界点、保安組織、使用区域を変更した場合 |
|
| 設置者について相続、合併又は分割があった場合 |
|
| 事業場を廃止した場合 (例)工場を閉鎖した、店を閉めた、ビルを売却し電力会社との契約を解除したなど |
|
| 発電所を廃止した場合 |
|
| 発電設備の一部を廃止した場合 |
|
| 需要設備のうち非常用予備発電装置(ばい煙発生施設)のみを廃止した場合 |
|
担当
電力安全課
- 電話
- 087-811-8585
- FAX
- 087-811-8595
- bzl-qsikps@meti.go.jp
関連するコンテンツ:
最終更新:2025年1月17日